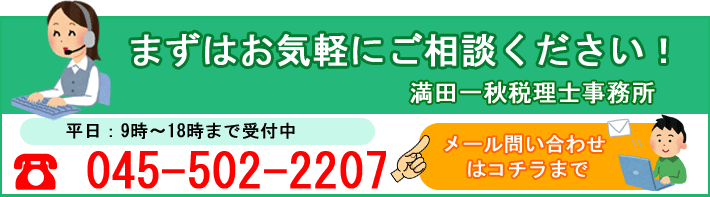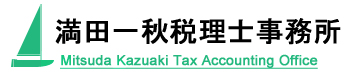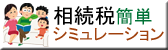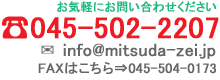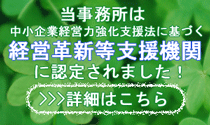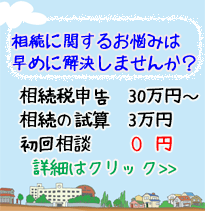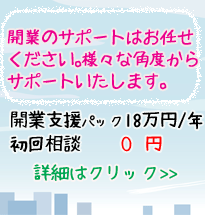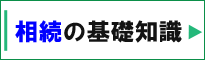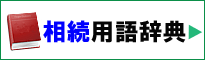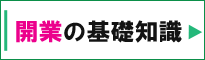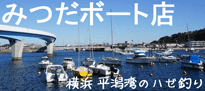6月, 2020年
- 2020-06-30☆☆☆7月のチェックポイント☆☆☆
- 2020-06-26国会で4月以降に成立した主な改正等は
- 2020-06-24納税の特例猶予の申請期限について
- 2020-06-22税務署等の処分に不服がある場合
- 2020-06-19第ニ次補正予算による雇調金の拡充等
- 2020-06-17大口・悪質な脱税者に実施される査察
- 2020-06-15住民税の決定通知書で控除額等を確認
- 2020-06-12特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税
- 2020-06-10感染防止とともに行う熱中症予防のポイント
- 2020-06-08来月10日施行、自筆証書遺言書保管制度
- 2020-06-05補正予算により実施予定の主な中小支援策
- 2020-06-03労働保険の年度更新と納付猶予の特例
- 2020-06-01☆☆☆ 6月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆7月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆7月のチェックポイント☆☆☆
※納期の特例の承認を受けている企業(従業員数が常時10人未満)の源泉所得税(1月~6月分)の申告・納付期限は7月10日(金)です。
※健保・厚年の「被保険者報酬月額定基礎届」の提出期限は7月1 0日(金)です。
※「労働保険の年度更新」の申告および保険料納付等の手続きは8月31日まで延長されます。
※新型コロナの第2波と熱中症が危惧されます。職場での3密防止、換気の確保、手洗い、テレワーク、時差通勤など、引き続き対策を。
国会で4月以降に成立した主な改正等は
国会で4月以降に成立した主な改正等は
閉会した第201回国会で、4月以降に成立した主な改正法等は次のとおりです(コロナ関連を除く)。
◎年金制度改正法・・・・・・
*短時間労働者を被用者保険 (厚生年金、健康保険)の適用対象とする事業所の規模要件(現行500人超)を段階的に引下げ、令和4年10月に100人超、令和6年10月に50人超とする、
*60~64歳の在職老齡年金制度について、支給停止となる基準額を47万円(現行28万円)に引上げる、
*年金の受給開始時期を60~75歳(現行60~70歳)の間で選択可能とする、
*確定拠出年金の加入可能年齡引上げなど。
◎中小企業成長促進法 (経営承継円滑化法などの改正)・・・・・・
中小企業が事業承継時に保証債務を借り換える場合や、他の事業者から事業用資産等を取得して事業承継(第三者承継)する場合に、経営者保証を不要とする信用保証制度を創設するなど。
◎道路交通法の改正・・・・・・
*本年6月30日から、あおり運転を取り締まる「妨害運転罪」を創設し、通行妨害目的で車間距離不保持や急な進路変更、急プレーキなどをした場合は懲役3年以下又は罰金50万円以下とし、著しい危険(高速道路での停車等)を生じさせた場合は懲役5年以下又は罰金100円以下とする、
*一定の違反歴がある75歳以上は、運転免許証更新時に運転技能検査を義務付けるなど。
◎著作権法等の改正・・・・・・
*違法にアップロードされた著作物へのリンク情報を集約したリーチサイト等の運営や、リンクを提供する行為を規制し罰則を科す、
*違法ダウンロード(違法にアップロードされたものだと知りながらダウンロードする行為)の対象を著作物全般に拡大するなど。
納税の特例猶予の申請期限について
納税の特例猶予の申請期限について
新型コロナの影響により、本年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期比概ね20%以上減少しており、一時に納税することが困難である場合は、無担保・延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられています。
この特例猶予は、本年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するものが対象となり、 納期限までに申請を行う必要がありますが、6月30日までは納期限後でも申請が可能です。
そのため、納期限が本年2月1日から6月30 日までに到来するものについては、6月30日が申請期限となります。
税務署等の処分に不服がある場合
税務署等の処分に不服がある場合
税務署長等が行った国税に関する処分に不服がある場合は、税務署長等に対する「再調査の請求」や、国税不服審判所長に対する「審査請求」により処分の取消しや変更を求めることができます (なお不服がある場合は裁判所に「訴訟」を提起)。
令和元年度に処理された「再調査の請求」のうち、納税者の主張が一部でも受け入れられた割合は12.4 % (処理件数1513件のうら187件)でした。また、「審査請求」については、13.2%(同2846件のうち375件)となっています。
第ニ次補正予算による雇調金の拡充等
第ニ次補正予算による雇調金の拡充等
今年度第ニ次補正予算が成立し、新型コロナに対した支援策が実施されます。
◆助成額の上限引上げなど、更なる拡充
雇用調整助成金の特例指置は、これまでに多くの拡允や申請手続きの簡素化などが行われており、今月12日時点での支給申請件数は累計16万4679 件(前日比9126件増)、支給決定件数は累計9万2616件(同5421件増)となっています。
今回の拡充は、緊急対期間を9月30日まで延長し、次の措置を本年4月1日に遡って適用します。
◎助成額の上限引上げ・・・・・・
企業規模を問わず、助成額の上限を1人1日あたり1万5千円(従来は8330 円)に引上げます。
◎解雇等を行わない中小企業の助成率の引上げ
解雇等を行わずに雇用を維持している中小企業の休業等に対する助成率を一律100%(従来は一定要件を満たす場合に100%)に引上げます。
◆既に支給された事業主にも遡及適用
上記の措置は、本年4月1日~9月30日までの期間の休業等が対象となり、既に支給された事業主などに対しても4月1日に遡って適用されます。
これに伴い、既に支給された事業主などに差額(追加支給分)が支払われますが、手続きは不要です。
(過去の休業手当を見直し、従業員に追加で休業手当の増額分を支給した場合には手続が必要)。
なお、雇用調整助成金の拡充のほか、小学校休業対応助成金・支援金の上限額引上げ等や、中小企の労働者が休業中に賃金の支払いを受けていない場合、労働者の申告で直接支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が創設されます。
大口・悪質な脱税者に実施される査察
大口・悪質な脱税者に実施される査察
査察は、一般の税務調査と異なり、国税査察官(いわゆるマルサ)が大口・悪質な脱税者に対して、刑事責任を追及する特別な調査です。
国税庁によると、令和元年度中に処理した事案は165件で、脱税額の総額は約120億円(1件あたり7300万円)でした。
そのうち116件を検察庁に告発しています(告発率70.3 %)。
なお、令和元年度中に査察事件の一審判決が言い渡された件数は124件で、その全てに有罪判法が出されています。
住民税の決定通知書で控除額等を確認
住民税の決定通知書で控除額等を確認
個人住民税は、前年の1月~12月までの所得等を基に計算された税額を、その翌年の6月から納付することになります。
昨年中にふるさと納税を行い、確定申告又はワンストップ特例制度を適用した方は、令和2年度の住民税が減額される形で控除されますので、住民税決定通知に記載された市町村民税(特別区民税)と道府県民税(都民税)の税額控除額を確認しましよう。
なお、新型コロナの影響により所得税の確定申告等の期限が延長されたため、申告内容が住民税額に反映されていない場合があります。その場合は後日、税額の変更通知が送付されます。
特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税
特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税
緊急経済対策における税制上の措置では、新型コロナの影響を受けた事業者に対して、公的貸付機関等(地方公共団体、政府系金融機関等)又は民間金融機関が特別に有利な条件で行う金銭の貸付けについて、「消費貸借契約書」の印紙税が非課税となる措置が設けられました(令和3年1月31日までに作成されるものに適用)。
既に該当する消費貸借契約の印紙税を納付している場合には、税務署に過誤納確認申請を行うことで印紙税額に相当する金額の還付が受けられます。
その際、申請書の提出とともに契約書等(原本)の提示又は過誤納となった事実を金融機関等が証明した書類(原本)の提出が必要となります。
感染防止とともに行う熱中症予防のポイント
感染防止とともに行う熱中症予防のポイント
新型コロナに伴い、マスクの着用や3密を避ける等を実践することが求められる中での、熱中症予防行動の留意点が取りまとめられています。
| ポイントは、 ①屋外で人と十分な距離が確保できる場合には、マスクをはずすようにする。 ② マスク着用時は負荷のかかる作業や運動を避け、人との距離を十分にとった上で適官マスクをはずして休憩する。 ③冷房時でも換気扇や窓開放によって換気を確保しつつ、工アコンの温度設定をこきめに調整する、などです。 |
来月10日施行、自筆証書遺言書保管制度
来月10日施行、自筆証書遺言書保管制度
◆法務局で自筆証書遺言書の保管が可能に
| 民法の相続に関するルールを大幅に見直した相読法の改正は、 ①自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日施行)、 ②預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、特別の寄与の制度など(令和元年7 月1日施行)、 ③配偶者居住権の創設など(令和2 年4月1日施行)と段階的に施行されています。 |
また、相続法の改正とともに成立した遺言書保管法が本年7月10日から施行となり、法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が開始されます。
自筆証書遺言は現状、自宅で保管するケースが多いことから、紛失や亡失、相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改さんのおそれがあるなどの問題がありますが、法務局に自筆証書遺言を預けることが可能になり、保管された遺言書は冢庭裁判所の「検認」が不要となります。
◆遺言者と相続続人等が行う主な手続き
遺言書の保管は全国の法務局で取り扱われ、遺言の住所地や本籍地、又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に対して申請できます。
なお、遺言者が亡くなる前に本人以外が保管した遺言書は閲等を行うことはできません。
遺言者が亡くなった場合、相続人等は法務局に遺言書保管事実証明書の交付を請求することで遺言書が保管されているかを確認することができ、保管された遺言書がある場合は、閲覧請求等ができます。
閲覧等が行われた場合は、その方以外の相続人等に対して遺言書が保管されている旨が通知されます。
なお、保管の申請や閲覧請求などは手数料がかかり、全ての手続きに予約が必要となります。
補正予算により実施予定の主な中小支援策
補正予算により実施予定の主な中小支援策
本年度の第2次補正予算案が閣議決定され、以下のような支援策の実施が予定されています。
◎日本公庫等による特別貸付の拡充・・・・・・
新型コロナウイルス感染症特別貸付等の貸付限度額を中小事業6億円・国民事業8千万円に、利下げ限度額(3年間0.9%引下げ)を中小2億円・国民4千万円に引上げます。
また、一定要件を満たす場合の利子補給による実質無利子化も中小2億円・国民4千円に引上げます。
◎民問金融機関における実質無利子・無担保融資の拡充・・・
都道府県等の制度融資を活用した民間金融機関の実無利子・無但保・保証料減免とする融資の限度額を4千万円に引上げます。
◎雇用調整助成金の拡充等・・・・・
| 雇用調整助成金の特例措置について、緊急対応期間を9月まで延長した上で、 *助成金の上限額を1日あたり1万5千円(現行8330円)に引上げ、 *解雇等を行わない中小企業の助成率を100%にします。 |
なお、中小企業の労働者が休業期間中に賃金の支払いを受けられなかった場合、労働者の申請により支援金を直接支給する制度を創設します。
◎家賃支援室支援給付金・・・・
テナント事業者(中堅・中小企業、個人事業者等)における本年5月~12月の売上について、「いずれか1カ月か前年同月比50%以上減少」、又は「連続する3カ月か前年同期比30%以上減少」の場合に、家賃の負担を軽減する給付金を創設します。
給付額は冢賃(月額)の2/3を6ヵ月分とし、給付上限額は法人300万円(月50万円)、個人事業者150万円(月25万円)です。
なお、複数店舗がある場合などは例外措置が設けられます。
労働保険の年度更新と納付猶予の特例
労働保険の年度更新と納付猶予の特例
労働保険(雇用・労災保険)は毎年、前年度の確定保険料と新年度の概算保険料の申告・納付を行う年度更新の手続きが必要ですが、本年度の年度更新期間は、新型コロナの影響を踏まえ、6月1日~8月31日まで延長されました。
また、本年2月以降の売上が前年同期比概ね20%以上減少している事業主は、申告により労働保険料等の納付を無但保・延滞税なしで1年間猶予する特例が適用できます(年度更新と併せて納付猶予の手続きが可能)。
なお、本年4月から64歳以上の高年齢労働者に対する雇用保険料の免除措置が終了し、高年齡労働者の賃金も雇用保険料の算定対象となります。
☆☆☆ 6月のチェックポイント☆☆☆
☆ ☆ ☆ 6月のチェックポイント☆ ☆ ☆
※感染防止対策
緊急事態宣言か全面解除され、経済活動を再開する段階になりましたが、業界ごとのカイドライン等を参考に感染防止対策に取り組みます。
※新年度個人住民税の特別徴収
6月支給の給与から、新年度個人住民税の特別徴収が始まるので、社員の住所地から通知された税額を賃金台帳に記入し徴収に備えます。
※健保・厚年の「算定基礎届」
提出期限は、7月10日(金)なので早めに取り掛かります。
※職場におけるパワハラ防止対策が義務
職場におけるパワハラ防止対策が義務付けられます (中小企業は令和4年3月まで努力義務)