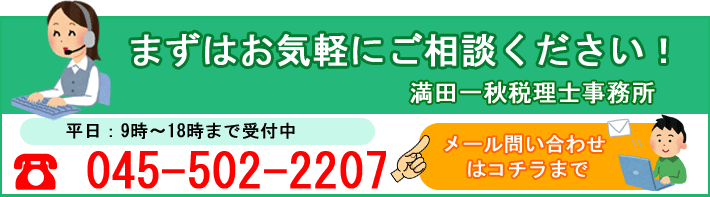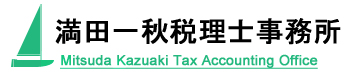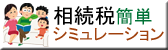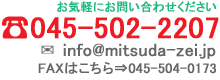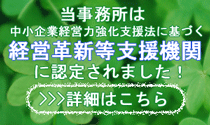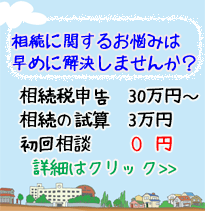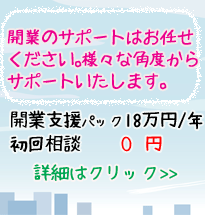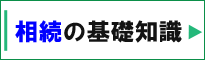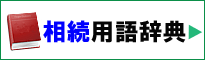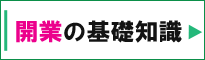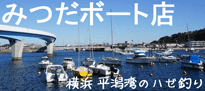7月, 2017年
- 2017-07-31★2017年8月のチェックポイント★
- 2017-07-28消費税が非課税となる取引は
- 2017-07-26マイナンバーの情報連携が試行運用開始
- 2017-07-24お祭などに協賛金を支出した場合は
- 2017-07-22取引相場のない株式の評価方法の基本
- 2017-07-20広告における不適切な「打ち消し表示」とは
- 2017-07-18高離者雇用に対する取組みが益々重要に
- 2017-07-14災害に関する税制上の取り扱い
- 2017-07-1228年度のふるさと納税は2844億円に
- 2017-07-10新体制での税務調査が始まります
- 2017-07-07相続等の土地評価額の基準となる路線価
- 2017-07-05来月から年金受給資格期間が10年以上に
- 2017-07-03★2017年7月のチェックポイント★
★2017年8月のチェックポイント★
※夏季休業を行う企業は、日程を取引先に通知すると同時に取引先の日程も確認して、納品・出荷や支払い・集金などを調整します。
※休業中の防犯対策や、パソコンなどのデータのバックアップを行います。
※夏季休業明けは疲労がたまる時期です。交通事故や労働災害などを防止するため、適度な休憩を設け健康管理と安全対策の徹底をします。
※台風や豪雨などに備え、商品・設備の水濡れ防止や緊急持ち出しなどの災害対策を。
消費税が非課税となる取引は
ビッ卜コインなどの仮想通貨が改正資金決済法 (今年4月施行)により支払の手段として位置づけられたこと等に伴い、今月から仮想通貨の売買取引ついては、消費税が非課税となりました。
◆非課税となる取引とは◆
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等の取引を課税の対象としていますが、課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、非課税となる取引が定められています。
例えば、支払手段や有価証券、物品切手等(商品券やプリペイドカードなど)の譲渡などは非課税取引となります。物品切手等については、最終的に商品券などを使用して商品・サービスの提供を受ける際、課税されることから二重課税を避けるために譲渡時には非課税とされています。
◆土地の譲渡や貸付けなども非課税取引◆
また、土地の譲渡や貸付け、住宅用としての建物の貸付けも非課税取引となります。
ただし、土地や住宅の貸付期間が1力月未満に満たない場合や、土地の貨付けについて駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税にはなりません。
なお、住宅の貸付けは、契約において人の居住用に供することが明らかなものが非課税となり、事務所などで貸し付ける場合の家賃は、課税対象となります。そのため、店舗等併設住宅については、住宅部分のみが非課税とされます。
マイナンバーの情報連携が試行運用開始
マイナンバ一を用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類(住民票の写しや課税証明書など)が省略できるように、異なる行政機関の間で情報をやり取りする情報連携が、今月18日から試行運用を開始し、秋頃から本格運用の開始が予定されています(試行運用期間中は、従来どおり書類の提出が必要)。
また、情報連携の試行運用に併せて、オンラインサービスのマイナポータルや子育てワンス卜ップサービスも試行運用が開始されました。
お祭などに協賛金を支出した場合は
夏祭りや花火大合が行われる季節になりましたが、事業と直接関係のない者が主催しているイベントに対して、協賛金を支出した場合は、原則として「一般の寄附金」となり、一定限度額の範囲内で損金算入できます。ただし、協賛企業として、*社名入りの提灯が吊るされる、*ホー厶ページや配布されるパンフレツ卜などに広告掲載があるなど、不持定多数に対する宣伝効果が期待できる場合は、広告宣伝費として全額損金になります。
一方、取引先など事業に関係する者が主催するイベン卜などに対して、今後の取引関係を維持することを目的に協賛金を支出した場合は、交際費等に該当します。
取引相場のない株式の評価方法の基本
29年度税制改正では、取引相場のない株式の評価について、類似業種比準方式における配当金額、利益金額、薄価純資産価額のウェイ卜の見直しや、評価会社の規模区分の金額等の基準の見直し等が行われ、29年1月以後の相続等により取得した財産評価に適用されます。
◆同族株主が取得した場合は原則的評価方式◆
取引相場のない株式の評価方法は、相続や贈与などで株式を取得した方によって異なり、議決権割合が30%以上であるグループ(株主とその同族関係者)に属している同族株主等が取得した場合は原則的評価方式、それ以外の方が取得した場合は特例的な評価方式(配当還元方式)により評価します。
原則的評価方式には、類似業種比準方式と純資産価額方式があり、類似業種比準方式は、事業内容が類似する複数の上場会社の株価の平均値に、評価会社と類似業種の1株当たりの配当、利益、純薄価純資産の比準割合を乗じて評価する方式です。
一方、純資産価額方式は、評価会社が仮に解散した場合の正味財産に基づいて評価する方式です。
◆会社の規模に応じた評価方法◆
原則的評価方式で評価する場合は、会社の規模に応じて大・中・小会社のいずれかに区分され、原則として、大会社の株式は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式、中会社はこれらの併用方式により評価します。
なお、会社の規模区分については、従業員数70人以上は大会社となり、従業員数70人未満の場合は総資産価額、従業員数、取引金額の基準により判定することになります。
広告における不適切な「打ち消し表示」とは
広告などで商品・サービスの内容や価格等を強調表示した際、例外や制約などがある場合は、その旨の表示(打ち消し表示)が必要となりますが、打ち消し表示は、目立たないように表示されていることがあります。
消費者疔は、打ち消し表示をしない広告が原則とした上で、不適切な表示として、「文字が見落とすほど小さい」、「文字が背景に紛れて目立たない」、「表示時間が短い」などの場合は景品表示法違反の可能性がある、との判断を示しました。
高離者雇用に対する取組みが益々重要に
29年版「高齡社会白書」によると、28年時点での全就業者数6465万人のうち、60〜64歳は8.1%、65〜69歳は6.8%、70歳以上は5.1% となっており、就業者に占める高齡者の割合は 年々増加しています。
企業には、高年齡者雇用安定法により「定年制の廃止」、「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を講じることが義務付けられていますが、高齡者に対する雇用環境整備などの取組みが益々重要となってきます。
なお、65歳以上への定年引上げや高齡者の雇用環境の整備等を実施する事業主を支援する制度として「65歳超雇用推進助成金」などがあります。
災害に関する税制上の取り扱い
福岡・大分県を中心とした記録的豪雨により、被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今般の災害により被害を受けた中小企業対策として、日本公庫等による災害復旧貸付や信用保証協会によるセーフティネッ卜保証、小規模企業共済制度の加入者に対する災害時貸付などが実施されます。
◆会社の資産が損害を受けた場合など◆
災害により商品や店舗などが滅失・損壊した場合の損失額や、損壊した資産の取壊し、土砂などを除去するための費用は損金になります。また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、原状回復のために補修などを行った埸合や、被災前の状態を維持するための補強工事などに支出した費用も修繕費として損金になります。
なお、災言を受けた取引先に対して、災害見舞金の支出や、事業用資産の供与などを行った場合の費用は、交際費等にはならず損金になります。
◆災害に対応する税制上の措置が常設化◆
29年度税制改正において、災害に対する税制上の措置が常設化され、法人税関係では「災害損失の繰戻しによる法人税額の還付」など震災特例法で手当てされていた措置の一部が常設化されました。
災害損失の繰戻し還付は、災害のあった日から1年を経過する日までの間に終了する各事業年度(又は災害のあった日から6月を経過する日までの間に終了する中間期間)において生じた災害損失欠損金額がある場合に、災言欠損事業年度開始の日前2年 (青色申告でない場含は前1年)以内に開始した事業年度の法人税額のうち、災害損失欠損金額に対応する一定額を還付請求できるというものです。
28年度のふるさと納税は2844億円に
総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」によると、28年度に行われたふるさと納税 (全地方団体合計)は、受入件数が1271万件(前年度比1.8倍)、受入額が2844億円(同1.7倍)と、増加しました。
このうち、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられるワンストップ特例制度(確定申吉をしない給与所得者等が行う5団体以内のふるさと納税が対象)を利用したのは、257万件・501億円となっています。
なお、地方団体別で受入額が最も多かったのは宮崎県都城市の73億円で、次いで長野県伊那市の72億円、静岡県焼津市の51億円と続きます。
新体制での税務調査が始まります
本日7月10日に、国税職員の定期人事異動が発令され、平成29事務年度が始まります。
新体制のもとで税務調査が始まりますので、何時来られても対応できるよう帳薄や領収書・契約書など証拠書類を整理しておきましょう。
税務調査は原則として、電話により事前通知(顧問税理士にも通知されます)がありますので、日時や対象税目・担当部門・調査官名などを聞きます。なお、日時等の都合が悪い場合には、正当な理由があれば変更することも可能です。
相続等の土地評価額の基準となる路線価
本日、相続税や贈与税において土地の評価額を算定する際の基準となる29年分の路線価(及び評価倍率)が公表されます。
◆相続等で取得した土地の評価方法は◆
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、相続等で取得した土地の評価方法は、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式は、路線価が定められている土地の評価方法で、路線価を土地の形状等に応じて補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。一方、 路線価が定められていない土地は評価倍率を用いた倍率方式となり、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出します。
なお、路線価等は、国税疔HPで閲覧できます。
◆居住用宅地等に係る「小規模宅地等の特例」◆
27年に相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられたため、土地等を相続する場合は「小規模宅地等の特例」を適用できるどうかがポイントとなります。
この特例は、被相続人(亡くなった方)の居住または事業用の宅地等を相続により取得した場合、一定要件を満たせば相続税評価頟を大幅に減額できる制度で、届住用宅地等であれば330㎡まで評価額を80%減額できます。
居住用宅地等について特例を適用できるのは、被相続人の配偶者や、被相続人と同居していた親族が取得した場合となりますが、配偶者や同居親族(法定相続人に限る)がいない場合で、相続開始前3年以内に自己所有の家屋に居住したことがない方であれば、同居していない親族でも適用できます。
来月から年金受給資格期間が10年以上に
老齡基礎年金は、受給資格期間を満たす場合に 原則65歳から受給できます。これまで受給資格期間は原則25年(300月)以上となっていましたが、改正年金機能強化法により、今年8月から原則10年(120月)以上あれば、老齡年金を受け取ることができるようになります。
なお、受給資格期間は、①国民年金や厚生年金の保険料を納付した期間(専業主婦など第3号被保険者の期間を含む)②国民年金保険料の納付免除等を受けた期間(免除等の種類によって受給額にも反映)、③国外居住していた場合などの合算対象期間(受給額には反映無し)、を合計した期間となります。
★2017年7月のチェックポイント★
※納期の特例の承認を受けている企業(従業員数が常時10人未満)の源泉所得税(1月〜6月分)は7月10日(月)が納付期限です。
※健保・厚年の「被保険者報酬月額算定基礎届」 の提出期間は7月1日〜10日です(来所日指定等の事業所を除く)。
※「労働保険の年度更新」の申告及び保険料納付等の手続は7月10日が期限です。
※夏場の健康管理に配慮します。特に、屋外での作業や外回りの社員には熱中症の注意を。